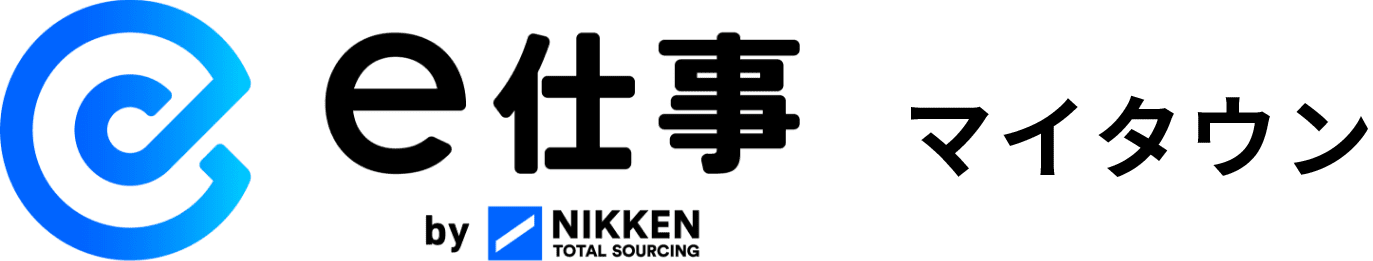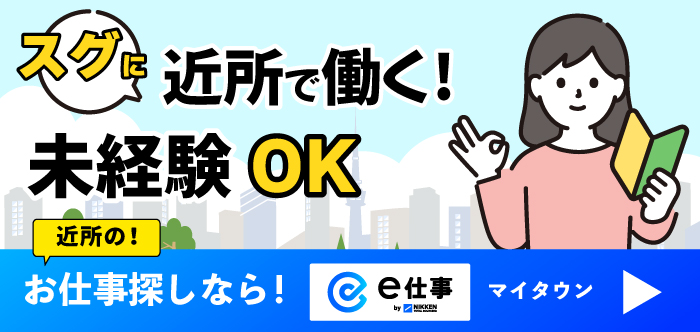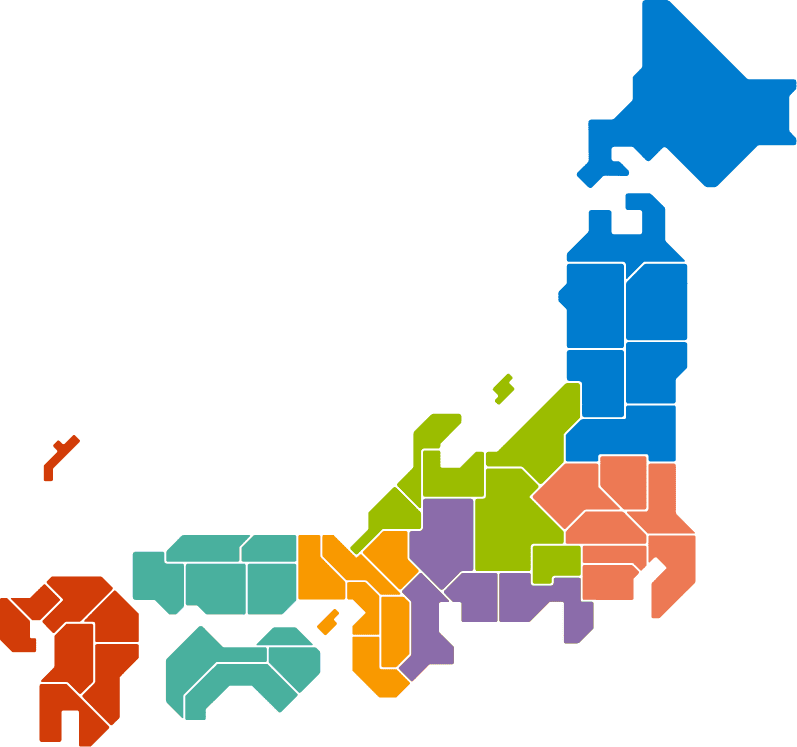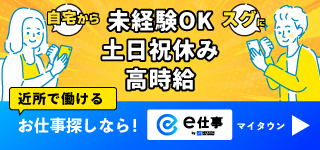仕分け作業とは?主な業務内容やピッキングとの違い、向いている人の特徴を紹介
2025/09/08
物流センターや倉庫で行われる仕分け作業は、私たちの生活を支える重要な仕事です。ECサイトで注文した商品が正確に届くのも、スーパーマーケットの商品棚が常に補充されているのも、この仕分け作業があってこそ実現しています。本記事では、仕分け作業の具体的な業務内容から求められる適性、将来性まで詳しく解説します。
仕分け作業の役割
仕分け作業は単なる荷物の整理にとどまらず、物流システム全体の効率性と品質を左右する重要な工程です。商品が生産者から消費者へ届くまでの過程において、仕分け作業は物流の要として機能しています。ここでは、仕分け作業が果たす4つの主要な役割について詳しく見ていきましょう。
倉庫内の整理整頓による作業効率の向上
仕分け作業による整理整頓は、物流センター全体の生産性を大きく左右します。商品や荷物を体系的に分類し配置することで、後続の作業工程が格段にスムーズになります。
例えば、佐川グローバルロジスティクスでは、Visual Warehouseシステムの導入により、わずか1ヶ月で生産性を23%向上させ、作業員の移動距離と時間を50%削減することに成功しました。これにより、経験の浅い作業員でもベテランと同等のパフォーマンスを発揮できるようになったといいます。
整理整頓された環境では、商品の探索時間が短縮され、作業ミスも減少します。日本の物流現場で広く採用されている5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の手法も、仕分け作業の効率化に大きく貢献しています。
正確な配送を支える品質管理の要
仕分け作業の精度は、顧客満足度に直結する重要な要素です。誤った仕分けは誤配送や配送遅延の原因となり、企業の信頼性を損なう可能性があります。
TONE株式会社の事例では、バーコード検証システムを活用した仕分け作業により、月間の出荷ミスを50件から10件未満に削減し、エラー率0.02%という驚異的な精度を達成しました。さらに半導体製造企業では、適切な仕分けとラベリングシステムにより、出荷精度を15倍改善し、99.999%の精度を実現しています。
このような高い品質管理基準は、日本の物流サービスが世界的に高い評価を受ける要因となっています。仕分け作業員一人ひとりの丁寧な作業が、日本の物流品質を支えているのです。
物流コスト削減への貢献
日本ロジスティクスシステム協会(JILS)の2024年データによると、製造業の物流コストは売上高の4.79%、卸売業では5.11%を占めています。この状況下で、仕分け作業の効率化はコスト削減の重要な手段となっています。
ある大規模WMS導入事例では、年間コストを6,498万円から4,331万円へと、実に2,167万円もの削減を実現しました。これは1日あたりの必要人員を22人から15人へと32%削減し、生産性を150%向上させた結果です。
正確な仕分けにより、誤出荷による再発送コストや、顧客からの問い合わせ対応にかかる人件費も削減できます。また、効率的な仕分け作業は残業時間の削減にもつながり、総合的な物流コストの最適化に貢献しています。
在庫管理の精度向上を実現する業務
仕分け作業により荷物がカテゴリーごとに整然と配置されることで、在庫数の把握や棚卸しが容易になります。整理された状態は在庫情報の誤りを減らし、在庫管理システムの精度向上にもつながります。
医療機器製造業者の事例では、適切な仕分けシステムの導入により、日々の在庫管理時間を2時間から24分へと80%削減し、IoT在庫管理により1日1,000〜2,000部品の処理を可能にしました。
小売チェーンでは、AI搭載の仕分けシステムにより8,000以上の製品SKUの管理を最適化し、需要予測精度の向上と最適な在庫レベルの実現を達成しています。
仕分け作業の業務内容
仕分け作業には様々な工程があり、それぞれに独自の手順や注意点があります。ここでは、実際の現場で行われている具体的な業務内容について、6つの観点から詳しく解説します。
荷物の仕分け基準と分類方法
仕分け作業では、あらかじめ定められた基準に従って荷物を分類します。主な分類基準には、配送エリア別、店舗・得意先別、商品カテゴリー別、緊急度や重量別などがあります。
分類方法は大きく3つのタイプに分けられます。在庫型は、センターに在庫がある商品を注文に応じて仕分ける方法で、ECサイトの物流センターで多く採用されています。通過型は、在庫を持たずに入荷された段階で仕分ける方法で、クロスドッキング施設で活用されています。製造型は、工場で製造された商品を仕分け場所で分類する方法です。
現場では、タブレット端末やマニュアルで指示された基準に従い、効率的かつ正確に仕分けを行います。
伝票番号・製品番号の照合と確認作業
仕分け時には、荷物に付いている伝票番号や製品番号を確認し、正しい行き先へ振り分ける作業が欠かせません。ヤマト運輸では12桁の識別番号、佐川急便では10桁または12桁の追跡番号を使用しています。
ベルトコンベアから流れてくる荷物のラベル情報を素早くチェックし、担当レーン番号に合った場所へ振り分ける作業は、高い集中力を要求されます。番号やラベルの文字が小さい場合もあるため、正確に読み取る注意力が必要です。
現代の物流センターでは、バーコードリーダーやハンディターミナルを使用した自動照合が主流となっており、作業の正確性と効率性が向上しています。
配送エリアや店舗別への振り分け作業
荷物を地域別、店舗別、トラック別のグループにまとめる振り分け作業は、効率的な配送を実現する上で極めて重要です。例えばヤマト運輸では、全国から送られてきた荷物を地域ごとに5つほどのエリアに仕分けし、大きな荷物の後にクール便の仕分けを実施しています。
Amazon千葉みなとFCでは、約3万台のポッドと約2,600台のドライブロボットが稼働し、梱包された商品は全国の配送拠点向けに自動仕分けされています。機械学習を活用し、各商品に最適なサイズの梱包資材を選定するシステムも導入されています。
手作業で行う場合は、台車やフォークリフトを使用し、バーコードリーダーで確認しながら慎重に作業を進めます。
大仕分けから中仕分けまでの段階的な作業工程
荷物が大量にある場合、段階的な仕分けにより効率を高めます。まず大仕分けで都道府県別などの大きな分類を行い、次に中仕分けで市町村別などのより細かい分類を実施します。
この段階的なアプローチにより、作業の並列化が可能となり、多くの作業員が同時に効率的に働けるようになります。例えば路線便では、集荷段階で行先ごとに一次仕分けを行い、長距離トラックへの積み付けのための大仕分けを実施。到着拠点での二次仕分けでは、さらに細かい配達エリアごとに中仕分けを行います。
このような体系的な仕分けプロセスにより、ミスの減少と作業効率の向上を両立させています。
コンベヤーシステムを使った荷引き作業
多くの配送センターでは、ベルトコンベアやソーター付きコンベヤなどの機械設備を活用した荷引き作業が行われています。作業者はコンベアから流れてくる荷物のラベルを確認し、自分の担当レーンに該当する荷物をピックアップします。
佐川急便の荷引き作業では、常に集中してラベル情報を確認し、担当レーンに荷物を引き込む必要があります。中腰姿勢での長時間作業となることが多く、体力的な負担も大きい作業です。
最新の施設では、人と機械のエリアを明確に分離し、透明シートシャッターやセーフティーフェンスなどの安全対策も充実しています。
繁忙期における作業量の変化と対応
物流業界には明確な繁忙期があり、年末年始(11月上旬〜1月上旬)は最も忙しい時期となります。クリスマス、お歳暮、年賀状などにより、通常の何倍もの貨物量となることがあります。
繁忙期には軽貨物ドライバーの場合、通常月60万円程度の売上が月100万円を超え、1日の配達件数も150件から200件超に増加します。物流センターでは、臨時スタッフの大量採用、作業時間の延長、自動化設備のフル活用などにより対応しています。
一方、閑散期には荷物が少なく早上がりになることもあり、シフトの柔軟な調整が重要となります。
仕分け作業とピッキング作業との違い
仕分け作業とピッキング作業は物流現場でよく混同されますが、それぞれ異なる役割と特徴を持っています。ここでは、両者の違いを4つの観点から明確にしていきます。
仕分けは分類・整理、ピッキングは収集・選別
仕分け作業は、届いた荷物や商品を決められたルールで分類・整理する業務です。一方、ピッキング作業は注文書に基づいて倉庫内から必要な商品を集める、つまり「ピックアップする」業務です。
英語の「pick」が「選ぶ・集める」を意味するように、ピッキングは個別の送り先に梱包する中身を選ぶ作業です。これに対し、仕分けはすでに梱包されたものを行き先別に分類する作業という明確な違いがあります。
この基本的な違いを理解することで、物流センターにおける作業フローの設計や人員配置の最適化が可能となります。
作業の流れにおける順序の違い
物流工程において、通常は「仕分け→ピッキング→品質チェック→梱包→出荷」という順序で作業が進行します。まずメーカーや問屋から入荷した商品を仕分けて棚卸しの準備をし、その後ピッキングで出荷指定の商品を集めていきます。
ただし、種まき方式(トータルピッキング)を採用する場合は、複数の注文を一括でピッキングし、その後に二次的な仕分け作業により個別の注文ごとに商品を分離するという流れになることもあります。
企業や現場によって順序や範囲が異なる場合もありますが、仕分けが基盤を作り、ピッキングが実際の出荷準備を行うという基本構造は共通しています。
扱う商品の状態の違い
仕分け作業では主に段ボール箱や梱包された荷物単位で作業することが多く、大きなパレットや箱詰めされた荷物をレーンごとに振り分ける場面が中心となります。
一方、ピッキング作業では棚やラックに並ぶ個々の商品を扱います。食料品や日用品などをバーコードリーダーで確認しながら袋詰めしたり、カートに集めたりする細かい作業が主体です。
扱う商品そのものは同じ物流センター内にある場合もありますが、仕分けは「発送前に梱包された荷物を整理」し、ピッキングは「出荷前の商品を収集」するという点で区別されます。
作業時の注意点の違い
仕分け作業では、一つのミスが連鎖的な影響を及ぼすため、落ち着いてミスなく仕分けることが最重要となります。他の人の作業や後工程に大きな負担をかける可能性があるため、正確性が特に重視されます。
ピッキング作業では、注文通りに商品をピックできているか、商品番号やバーコードの照合が注意点となります。スピードも大切ですが、指定通りの商品を抜けなく集めることが求められます。
両者とも正確性は重要ですが、仕分けは「システム全体への影響」を、ピッキングは「個別注文の完全性」を特に意識する必要があります。
仕分け作業に向いている人
仕分け作業は誰でもできる仕事のように見えますが、実際には向き不向きがはっきりと出る仕事です。ここでは、仕分け作業に適性がある人の特徴を6つの観点から解説します。
体を動かすことが好きで基礎体力がある人
仕分け作業では、軽いものから時には重い箱まで様々な荷物を扱います。長時間の立ち仕事が基本となり、倉庫内を歩き回ることも多いため、基礎体力は必須条件です。
ある物流企業の作業者は「倉庫の中では汗をいっぱいかきますし、荷物が重いのでかなり体力が必要な仕事ですが、仕分け作業が早くて上手になったと褒められると、そういった言葉が作業の励みややりがいになります」と語っています。
スポーツ経験者や体力に自信のある人は現場で重宝され、仕事を通じて体力がついたことを実感する人も多くいます。
黙々と集中して単純作業を継続できる人
仕分け作業は同じ動作の繰り返しになるため、ルーティンワークに抵抗がない人に適しています。仕分け中は一人で黙々と作業を進める場面が多く、電話対応や接客などの対人コミュニケーションはほとんどありません。
20代男性の作業者は「人とあまりコミュニケーションを取らなくていいので、ストレスなく作業できました。やっていくうちにどんどん作業にのめり込んでいって、黙々とこなしていくうちにあっという間に時間が過ぎている感覚でした」と体験を語っています。
周りの雑音に惑わされず、淡々と荷物の仕分けに集中できる人は、この仕事で成果を上げやすいでしょう。
細かい作業や整理整頓が得意な人
仕分けでは荷物のラベルや数字など小さな表示を正確に読み取る場面が多くあります。誤りを防ぐには、細部への注意力が不可欠です。
製品コードと配送先住所の読み取りと照合の正確性、詳細なルールに従った商品分類能力、出荷エラー防止のための細部への注意など、様々な場面で丁寧さが求められます。
自分の作業エリアを常にきちんと整理整頓できる人は効率的に作業を進められ、物の取り違えや置き忘れが少なく済み、作業全体の流れがスムーズになります。
作業の効率化や改善を楽しめる人
仕分け作業は単純ながらもコツがあり、働きながら手順を工夫して効率を上げる余地があります。慣れてくると自分なりに段取りを工夫してミスを減らしたり、スピードを上げたりできます。
身体の動きと位置取りによるワークフローの最適化を学び、経験を通じてより速く正確な仕分け方法を開発することで、働く充実感を感じられます。
「いかにスピーディーに、そして正確に荷物や商品を仕分けできるか」という課題に取り組むことで、仕事の達成感も高まります。
未経験やブランクがあっても新しい仕事に挑戦したい人
仕分け作業には特殊な資格や経験は必要ありません。作業自体がシンプルで、一度覚えてしまえば難しくないため、未経験でも取り組みやすい仕事です。
30代女性の作業者は「副業で仕分けバイトをしています。シフトの融通が聞きやすいので、本業との調整がしやすく、空いた時間にお小遣い稼ぎができるのでとても助かってます」と話しています。
10代から60代までの幅広い年齢層が活躍しており、他業種からの転職やブランク明けの方でも応募しやすい環境が整っています。
柔軟なシフトで自分のペースで働きたい人
仕分け作業は24時間稼働している配送センターも多く、深夜帯も含めて多様な時間帯で働けます。週1〜3日という柔軟な週間スケジュールも可能で、ライフスタイルに合わせてシフトを組みやすいのが魅力です。
学生が授業のない土日だけ、主婦が早朝の数時間だけ、フリーターが深夜に集中してなど、自分のペースに合わせて働けます。深夜帯は時給が高くなることが多く、22時から5時の勤務では時給が1.25倍になり、最大2,000円になることもあります。
40代女性は「軽作業なので、他のアルバイトに比べるとかなり負荷の少ない仕事だと思います」と評価しています。
仕分け作業を通じて得られるスキルと将来性
仕分け作業は、日本の物流インフラを支える重要な仕事として、今後も安定した需要が見込まれています。EC市場の拡大により物流需要は増加を続けており、AI化や自動化が進む中でも、人間にしかできない品質管理や例外処理の業務は残り続けます。
この仕事を通じて身につく正確性、集中力、効率化スキルは、物流業界でのキャリアアップの基盤となります。フォークリフト免許などの資格取得により専門性を高めることも可能で、作業員からチームリーダー、管理者へとステップアップする道も開かれています。
仕分け作業は、未経験から始められる仕事でありながら、物流の基礎を学び、将来のキャリアを築ける可能性を秘めた職種です。体力と集中力を活かして働きたい方、柔軟なシフトで自分のペースを大切にしたい方にとって、検討する価値のある選択肢といえるでしょう。
近所のお仕事探しは求人サイト「e仕事マイタウン」がおすすめ!
工場・製造業のお仕事に興味がある人は求人サイト「e仕事」がおすすめ!
例えば
- 未経験OK
- 土日休み
- 高時給
など様々な求人があります。無料で利用できるのでぜひチェックしてみてくださいね。
e仕事マイタウンはこちらから↓↓↓
求人カンタン検索
こだわりのメリットでカンタン検索。希望の条件をクリックして下さい。
都道府県で探す
業種で探す
こだわり条件で探す
- 待遇
- 働き方
- 募集条件
- 職場環境