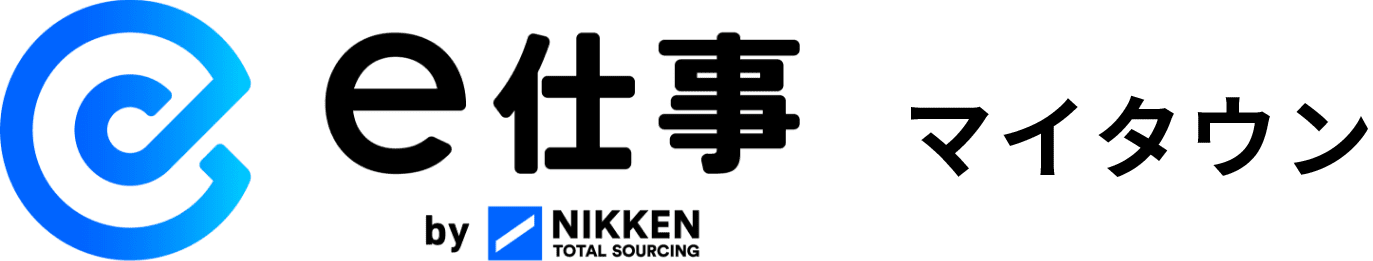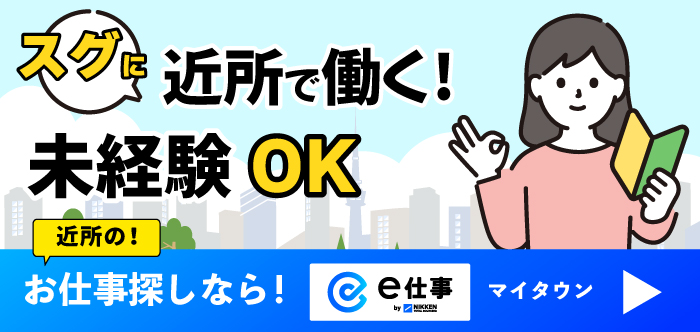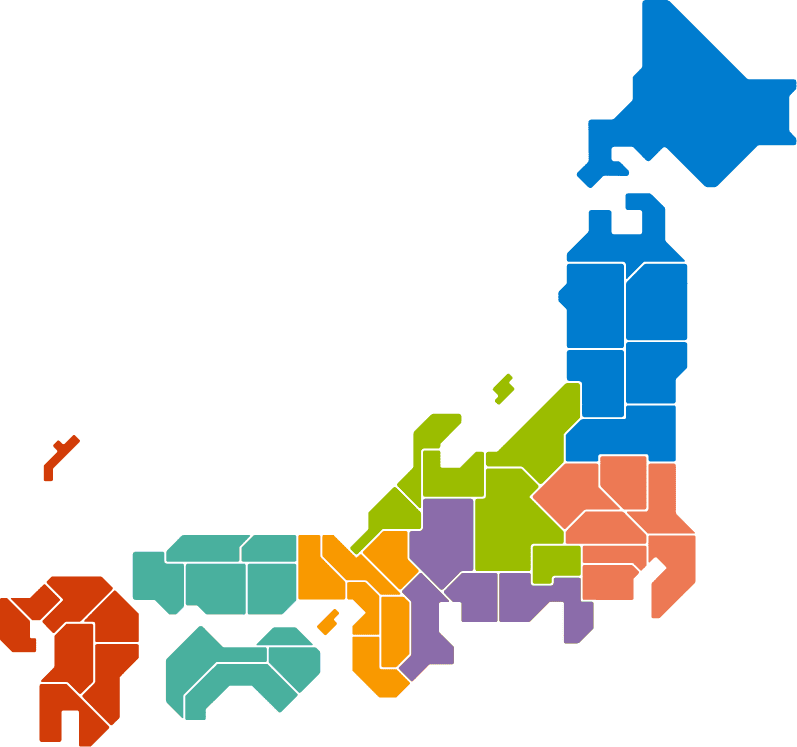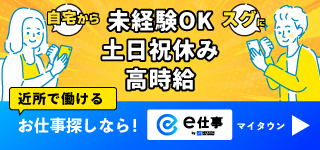溶接作業とは?種類や手順、注意点などを解説。向いている人とは?
2025/09/08
金属と金属を強固に結びつける溶接作業は、私たちの暮らしを支える重要な技術です。建築物の鉄骨から自動車のボディ、橋梁から家電製品まで、あらゆる場面で溶接技術が活用されています。本記事では、溶接作業の基本知識から実際の作業手順、安全上の注意点、必要な資格、そして溶接工に向いている人の特徴まで、幅広く解説していきます。
溶接作業の基本知識
溶接は金属を接合する技術として産業界で欠かせない存在となっています。その種類や方法は多岐にわたり、用途や材料に応じて使い分けられています。まずは溶接の基本的な概念から、実際の現場で活用される技法まで確認していきましょう。
溶接作業とは何か
溶接作業とは、複数の金属部材を熱エネルギーや圧力を用いて原子レベルで結合させる加工技術です。単にくっつけるだけでなく、母材と呼ばれる金属同士が溶け合って一体化することで、非常に高い強度を実現できます。
ボルトやリベットによる機械的な接合と比較すると、溶接は継ぎ目がなく気密性に優れ、振動にも強いという特徴があります。一方で、一度溶接した部分は分解や交換が困難であり、作業には高い技術と専門知識が求められます。
現代社会において溶接技術なしに成り立つ産業はほとんど存在しません。高層ビルの骨組みから精密機器の微細な部品まで、規模や精度は異なれど、金属を扱うあらゆる分野で溶接作業が行われています。
溶接方法の3つの基本分類
溶接方法は、金属を接合する際のエネルギーの与え方によって大きく3つに分類されます。
「融接(ゆうせつ)」
接合部の金属を高温で溶かして一体化させる方法です。電気アークやガス炎、レーザー光などを熱源として使用し、必要に応じて溶加材と呼ばれる追加の金属を加えながら接合します。最も一般的な溶接方法であり、厚い鋼材から薄板まで幅広く対応できます。
「圧接(あっせつ)」
金属同士を強い圧力で押し付けて接合する方法です。加熱を併用する場合もありますが、母材を完全に溶かすことなく、原子間の結合力を利用して一体化させます。自動車の生産ラインで使われるスポット溶接が代表例で、短時間で大量の接合が可能です。
「ろう接」
母材よりも融点の低い金属(ろう材)を溶かして接着剤のように使う方法です。450度以上の温度で行うろう付けと、それ以下の温度で行うはんだ付けに分かれます。母材にダメージを与えずに接合でき、異種金属の接合にも適していますが、融接ほどの強度は得られません。
現場でよく使われる溶接技法
実際の製造現場や建設現場では、作業内容や材料に応じて様々な溶接技法が使い分けられています。
被覆アーク溶接
最も基本的な手法として広く普及しています。被覆材で覆われた溶接棒を手で操作しながら、電気アークで金属を溶かして接合します。設備が比較的簡単で、屋外作業にも適していますが、作業者の技量によって品質が大きく左右されます。
半自動アーク溶接(MAG/MIG溶接)
ワイヤが自動的に送り出される仕組みを持つ効率的な方法です。シールドガスで溶接部を保護しながら作業するため、美しい仕上がりが期待できます。工場内での大量生産に適しており、現在最も普及している溶接方法の一つです。
TIG溶接
タングステン電極を使用した精密な溶接方法です。スパッタが飛ばず、薄板やステンレスなどの美観が求められる部分に最適です。ただし、高度な技術が必要で、作業速度は他の方法と比べて遅くなります。
このほか、レーザー溶接や電子ビーム溶接といった最新技術も、精密部品の製造などで活用されています。
溶接作業の主な手順
溶接作業は単に金属を溶かして接合するだけでなく、綿密な準備から品質確認まで、複数の工程を経て完成します。各工程を適切に実施することで、安全で高品質な溶接が実現できます。
図面の読み取りと作業計画
溶接作業の第一歩は、製品図面に記載された溶接記号を正確に読み取ることから始まります。図面には、どの部分をどのような方法で溶接するか、溶接ビードのサイズや形状はどうするかといった詳細な指示が記号で示されています。
これらの情報を基に、作業の順序や使用する機材を決定します。大型構造物では、溶接による熱収縮でゆがみが生じやすいため、対称位置を交互に溶接するなど、ひずみを最小限に抑える工夫が必要です。
また、母材の材質や板厚に応じて、適切な溶接方法と条件を選定します。例えば、厚い鋼板にはアーク溶接、薄いステンレス板にはTIG溶接といった具合に、最適な手法を選ぶことが品質向上につながります。
部材の加工と段取り
図面通りの寸法に部材を切断し、必要に応じて開先(かいさき)と呼ばれるV字型の溝を加工します。開先は厚い板を突き合わせ溶接する際に、十分な溶け込みを確保するために必要な加工です。
次に、治具やクランプを使って部材を正確な位置に固定します。この際、仮付け溶接(タック溶接)を数か所行い、本溶接中に部材がずれないようにします。仮付けは小さく、本溶接の邪魔にならない位置に施すことが重要です。
溶接面の清掃も欠かせません。油分やさび、塗料などが残っていると溶接欠陥の原因となるため、グラインダーやワイヤーブラシで丁寧に除去します。
溶接施工の実施
準備が整ったら、いよいよ溶接作業に入ります。まず溶接機の設定を確認し、適切な電流・電圧に調整します。防護具を着用し、周囲の安全を確認してから作業を開始します。
アーク溶接の場合、溶接棒を母材に軽く接触させてアークを発生させます。安定したアークを維持しながら、一定の速度と角度で溶接線に沿って進めていきます。溶融池の状態を観察しながら、適切な溶け込み深さとビード幅を保つことが重要です。
厚板の場合は、一度に全断面を溶接するのではなく、複数回に分けて溶接ビードを重ねる多層溶接を行います。各層の間では、スラグを除去し、適切な層間温度を維持しながら作業を進めます。
仕上げ処理
溶接が完了したら、ビード表面に付着したスラグをチッピングハンマーで除去します。スラグは溶接棒の被覆材が溶けて固まったもので、これを取り除くことで初めて溶接部の状態を確認できます。
必要に応じて、グラインダーで余分なビードを削り、表面を滑らかに整えます。構造物の用途によっては、完全に平らに仕上げたり、角を丸めたりすることもあります。
作業後は、火の後始末を忘れてはいけません。溶接の火花が原因で時間差で火災が発生することもあるため、作業場所を離れる前に30分から1時間程度は監視を続けることが推奨されています。
検査と品質確認
すべての溶接が終わったら、品質検査を実施します。まず目視検査で、割れやピンホール、アンダーカットなどの表面欠陥がないか確認します。溶接ゲージを使って、ビードの高さや脚長が規定値内に収まっているかも測定します。
重要な構造物では、非破壊検査も実施されます。超音波探傷試験やX線検査により、内部の溶け込み不良や空洞などを発見できます。検査で不合格となった箇所は、再溶接や補修を行い、再度検査を実施します。
すべての検査に合格して初めて、溶接作業は完了となります。品質記録は保管され、後々のトレーサビリティに活用されます。
溶接現場で注意すべき点
溶接作業は高温の火花や有害物質を扱うため、様々な危険が潜んでいます。安全に作業を行うためには、これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。
火傷・眼障害のリスク
溶接時に発生する高温のスパッタは、皮膚に直接触れると深刻な火傷を引き起こします。また、溶接直後の母材は数百度の高温になっており、うっかり触れてしまうと重度の熱傷を負う危険があります。
アーク溶接で発生する強烈な紫外線は、無防備な目で見ると角膜に炎症を起こす「電気性眼炎」を引き起こします。症状は数時間後に現れ、激しい痛みと涙が止まらなくなります。最悪の場合、視力低下や失明の危険もあります。
これらを防ぐため、適切な遮光度の溶接面と、耐熱性の革手袋・防護服の着用が必須です。周囲で作業する人も、溶接光を直視しないよう注意が必要です。
ヒューム吸入による健康被害
溶接作業中に発生する溶接ヒュームには、微細な金属粒子が含まれています。これを長期間吸入し続けると、肺に蓄積して「じん肺」と呼ばれる呼吸器疾患を引き起こす可能性があります。
2021年4月からは、金属アーク溶接作業で発生するヒュームが特定化学物質として規制対象となりました。事業者には作業環境測定の実施と、測定結果に基づく換気装置の設置が義務付けられています。
作業者は国家検定に合格した防じんマスクの着用が必須となり、定期的な特殊健康診断の受診も義務化されています。密閉空間での作業では、送気マスクの使用も検討する必要があります。
感電・爆発の危険性
アーク溶接では高電圧・大電流を扱うため、感電の危険が常に存在します。溶接機の二次側無負荷電圧は80V以上になることもあり、濡れた手袋や破損したケーブルから感電すると、心室細動を起こして命に関わる事故につながります。
ガス溶接では、高圧ガスボンベの取り扱いを誤ると爆発事故の危険があります。逆火現象(炎がホース内に逆流する現象)による火災や、可燃性ガスの漏洩による爆発事故も報告されています。
これらを防ぐため、作業前の機器点検、絶縁手袋の着用、ガスボンベの適切な管理が重要です。タンク内部など密閉空間での作業では、残留ガスの完全な除去も必要です。
過酷な作業環境の問題
溶接現場は決して快適な環境とは言えません。夏場は溶接熱と外気温のダブルパンチで熱中症のリスクが高まり、冬場は寒風にさらされながらの作業となります。
狭いタンク内部や高所での作業では、無理な姿勢を長時間維持しなければならず、腰痛や筋肉痛の原因となります。グラインダーやハンマーの騒音は聴力に影響を与える可能性もあります。
事業者には、適切な休憩時間の設定、換気設備の整備、防暑・防寒対策の実施など、作業環境の改善が求められています。作業者自身も、体調管理と水分補給を心がける必要があります。
溶接工として働くために必要な資格
溶接の仕事に従事するには、法律で定められた資格の取得が必要です。基本的な資格から上位資格まで、段階的にスキルアップしていくことでキャリアの幅が広がります。
基本資格:アーク溶接作業者
アーク溶接を行うためには、労働安全衛生法に基づく「アーク溶接等の業務に係る特別教育」の修了が必須です。18歳以上であれば誰でも受講でき、学科11時間、実技10時間程度の講習を受けることで資格を取得できます。
講習内容は、溶接機の構造や取り扱い方法、感電・火災の防止対策、作業方法の基礎などです。修了試験の合格率はほぼ100%で、一度取得すれば生涯有効です。
2024年からは、金属アーク溶接作業を行う事業場では「金属アーク溶接等作業主任者」の選任が義務化されました。主任者になるには、特別教育修了者が追加の技能講習を受ける必要があります。
基本資格:ガス溶接技能者
ガス溶接・ガス切断を行うには「ガス溶接技能講習」の修了が必要です。18歳以上で受講可能で、学科と実技を合わせて2日間程度の講習となります。
講習では、可燃性ガスと酸素の取り扱い、火炎の調整方法、関係法令などを学びます。修了試験に合格すると、都道府県労働局長から技能講習修了証が交付されます。
現場で責任者となるには、3年以上の実務経験を積んだ後、「ガス溶接作業主任者」の免許試験に合格する必要があります。
スキルアップ資格:JIS溶接資格・技能士
日本溶接協会が実施する「溶接技能者評価試験」は、溶接技術のレベルを証明する重要な資格です。手溶接、半自動溶接、ステンレス溶接、アルミニウム溶接など、9種類の区分があります。
各区分は基本級と専門級に分かれており、実技試験と学科試験の両方に合格する必要があります。民間資格ですが、多くの企業がJIS溶接資格保持者を優遇しており、転職や昇進に有利に働きます。
国家検定である技能士制度にも溶接関連の職種があり、1級から3級まで段階的に受験できます。技能士の称号は公的な技能証明として高く評価されています。
上位資格:溶接管理技術者
キャリアを積んだ溶接技術者には、日本溶接協会の「溶接管理技術者」資格があります。特別級、1級、2級の3段階があり、溶接施工の計画・管理・品質保証の能力を証明します。
受験には学歴と実務経験が必要で、試験の難易度も高いですが、合格すれば溶接のエキスパートとして認められます。大規模プロジェクトでは、溶接管理技術者の配置が入札条件となることもあります。
「溶接作業指導者」資格は、現場での教育・指導能力を認定するもので、25歳以上の溶接技能者が対象です。この資格を持つと、社内教育や職業訓練校での講師として活躍できます。
溶接作業に向いている人の特徴
溶接工として成功するには、技術的なスキルだけでなく、性格や資質も重要な要素となります。どのような人が溶接作業に適しているのか、主な特徴を見ていきましょう。
集中力と手先の器用さ
溶接作業では、アークの長さや移動速度をミリ単位でコントロールする必要があります。わずかな手ぶれや注意散漫が、溶接欠陥につながる可能性があります。
長時間同じ姿勢で、単調な作業を続けても集中力を維持できる忍耐強さが求められます。また、狭い場所や見えにくい位置での溶接では、手先の感覚だけで作業を進める器用さも必要です。
細かい作業が得意で、コツコツと丁寧に仕事を進められる人は、美しく強固な溶接ビードを作り出すことができるでしょう。逆に、大雑把で飽きっぽい性格の人には向かない仕事と言えます。
体力と粘り強さ
溶接工の仕事は肉体労働の側面が強く、重い鋼材を扱ったり、一日中立ちっぱなしで作業したりすることが日常的です。夏場の工場では、防護服を着用した状態で高温の溶接作業を行うため、相当な体力を消耗します。
技術の習得にも時間がかかり、一人前になるまでには数年の修行期間が必要です。すぐに結果が出なくても、諦めずに練習を重ねる粘り強さが求められます。
体を動かすことが好きで、多少の困難にも負けない強い精神力を持つ人は、溶接工として長く活躍できるでしょう。
段取り力と適応力
効率的な溶接作業には、事前の計画と準備が欠かせません。図面を読み解き、作業手順を組み立て、必要な材料や工具を揃える段取り力が重要です。
現場では予期せぬトラブルも発生します。部材が図面通りに合わない、天候の影響で条件を変更する必要がある、急な設計変更が入るなど、臨機応変な対応が求められる場面も多くあります。
新しい溶接技術や機材の導入にも前向きに取り組める柔軟性があれば、技術革新が進む業界でも活躍し続けることができるでしょう。
溶接業界の将来性
溶接技術は産業の基盤を支える重要な技術であり、将来的にも安定した需要が見込まれています。技術革新と人材不足の両面から、溶接工の価値は今後さらに高まると予想されています。
インフラ維持での継続的需要
日本では高度経済成長期に建設された橋梁やトンネル、ビルなどのインフラが一斉に老朽化の時期を迎えています。国土交通省によると、建設後50年を経過する橋梁の割合は、2033年には約63%に達する見込みです(国土交通省「インフラメンテナンス情報」)。
これらの構造物の補修・補強には、腐食部分の交換や補強材の追加など、溶接技術が不可欠な作業が多く含まれます。地震対策としての耐震補強工事でも、既存構造物への補強部材の溶接が必要です。
国土強靭化計画により、今後も継続的にインフラ整備予算が投入される見通しで、溶接工の仕事は安定的に存在し続けるでしょう。
新エネルギー分野での需要拡大
カーボンニュートラル実現に向けて、再生可能エネルギー設備の建設が加速しています。風力発電のタワーや洋上風力の基礎構造物、太陽光パネルの架台など、すべて溶接技術が必要です。
水素社会の実現に向けた高圧タンクや配管の製造、電気自動車向けの新素材部品の接合など、新たな分野での溶接需要も生まれています。
これらの新技術に対応するには、従来とは異なる材料や工法の知識が必要となり、専門性の高い溶接技術者の価値はさらに高まることが予想されます。
AI時代でも必要とされる技術
製造業では溶接ロボットの導入が進んでいますが、すべての溶接作業が自動化できるわけではありません。複雑な形状の構造物や、現場での補修作業、一品ものの特注品など、人間の判断と技術が必要な領域は数多く残されています。
むしろロボットを操作・管理する技術者として、溶接の知識と経験を持つ人材の需要は高まっています。デジタル技術と伝統的な溶接技能の両方を備えた人材は、今後ますます重宝されるでしょう。
品質の最終判断や、微妙な調整が必要な作業は、依然として人間の経験と勘に頼る部分が大きく、熟練工の価値は変わりません。
若手不足による市場価値向上
溶接業界では深刻な人材不足が続いています。ベテラン技能者の大量退職時期を迎える一方、若手の入職者が少ないため、技能継承が大きな課題となっています。
この状況は、技能を持つ溶接工にとってはチャンスでもあります。企業は優秀な人材を確保するため、待遇改善や福利厚生の充実を図っており、溶接工の労働条件は着実に向上しています。
若いうちから溶接技術を身につけ、資格を取得していけば、将来的に高い市場価値を持つ人材として活躍できる可能性が高いでしょう。
溶接工への道を検討する際のポイント
溶接工を目指す際は、仕事の実態を正しく理解し、必要な準備を整えることが大切です。肉体的にハードで危険も伴う仕事ですが、社会インフラを支える重要な役割を担い、技術を磨けば安定したキャリアを築くことができます。
まずは基本資格の取得から始め、実務経験を積みながら上位資格に挑戦していくことで、着実にスキルアップできるでしょう。安全意識を常に持ち、新しい技術にも積極的に取り組む姿勢があれば、AI時代においても必要とされる溶接技術者として長く活躍できるはずです。
近所のお仕事探しは求人サイト「e仕事マイタウン」がおすすめ!
工場・製造業のお仕事に興味がある人は求人サイト「e仕事」がおすすめ!
例えば
- 未経験OK
- 土日休み
- 高時給
など様々な求人があります。無料で利用できるのでぜひチェックしてみてくださいね。
e仕事マイタウンはこちらから↓↓↓
求人カンタン検索
こだわりのメリットでカンタン検索。希望の条件をクリックして下さい。
都道府県で探す
業種で探す
こだわり条件で探す
- 待遇
- 働き方
- 募集条件
- 職場環境